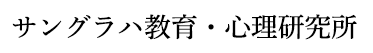会報誌「サングラハ」今号の内容についてご案内致します。
2025年3月25日発行、全頁、A5判、700円
目次
巻頭言 … 2
『サングラハ』誌第二〇〇号の刊行にあたり … 岡野守也 … 3
サングラハに魅せられて … 高世仁 … 7
創刊第二〇〇号記念寄稿集「サングラハと私の学び」 … 12
ヒューマン・ギルド・ニュースレターより … 高世仁 … 52
「サングラハ応援プロジェクトへの感謝と新たなご案内」
「著者による本の紹介:『ウクライナはなぜ戦いつづけるのか
~ジャーナリストが戦場で見た市民と愛国』(旬報社)」
講座・研究所案内 … 55
巻頭言
研究所主幹代理 高世 仁
会報『サングラハ』が一九九二年二月の創刊第一号から三十三年を迎え、今号が第二〇〇号となりました。
初心忘るべからずという言葉がありますが、この機会に創刊号所収の「研究所設立趣意書」(九二年一月八日)を読んでみました。そこには岡野守也主幹が目指す研究所の目的がこう記されています。
◇どうしたら、人間すべてが、自分自身とも他者とも自然とも調和した、「仲良く楽しく生きて楽に死ぬ」ことができるような生き方に到達できるか、徹底的な探求を試みること。
◇そのためには、近代的な理性・科学主義、個人主義、ヒューマニズムは不十分であり、霊性と理性の統合、自己実現から自己超越へという意味での〈意識の変容〉が必要条件―十分条件ではない―だと思われるので、そのための理論と方法とそしてなによりも実践そのものを探求すること。
◇その時その時に到達した探求の成果を、自己絶対化することなく仮説・試案・提案といったかたちで、しかしやはり広く社会に提示していくこと。
◇そのことによって、人類の全体的変容―サヴァイバルになにほどか貢献すること。
いま私たちの生きている時代は、おそらく人類史における転換点にあります。パレスチナやウクライナをはじめ世界各地で殺戮が続き、温暖化による異常気象と気候難民の増加に歯止めがかかりません。その結果、地球の危機を自覚しない「自国ファースト」のリーダーが次つぎに輩出し、人類同士の対立が先鋭化しています。
その一方で「自分さえよければ」のエゴイズムは、協同して危機を回避する努力を阻害しています。
私たちの心と地球の危機が深化してきた今、〈人間すべてが、自分自身とも他者とも自然とも調和した、「仲良く楽しく生きて楽に死ぬ」ことができるような生き方に到達できる〉ようにしたいとの岡野主幹の願いは、より切実に胸に迫ってきます。
岡野主幹の思想的達成を受け継ぎ、サングラハ教育・心理研究所の学び、探求、発信を継続し、人類の「サヴァイバル」に少しでも貢献すべく歩み続けたいとの思いをあらたにしました。
『サングラハ』誌第二〇〇号の刊行にあたり
研究所主幹 岡野守也
第二〇〇号の刊行にあたり、最初に長年にわたってサングラハ教育・心理研究所の歩みを支えてくださった皆様に心からお礼を申し上げたいと思います。サングラハは皆様のおかげ・力・ご縁で成り立ち、持続することができています。とりわけ主幹の病気以降、たくさんの方から物心ともに多大なご支援をいただいていること、深く深く感謝しております。お一人ひとりにお礼を申し上げることができていませんが、どうぞご海容ください。
さて、以下改めてお伝えしておくと、長年にわたる私の思想的・実存的探究には、五つの原点というか出発点がありました。
(以下、本誌並びにこちらにて全文掲載)

サングラハに魅せられて
研究所主幹代理 高世 仁
私が岡野守也主幹の思想にはじめて触れたのは一九九四年のことでした。どのようにしてサングラハにたどり着いたのか、自分の思想的変遷を振り返ってみたいと思います。
私が左翼だったころ
もう半世紀近く前、大学を卒業した私は、高校時代の友人と数年ぶりに会っていた。友人は名の知れた大手証券会社に就職したと聞いていたのだが、一年もたたずに退社していた。
個人の営業成績がグラフで壁に貼りだされる激しい社内競争と過酷な業務管理にさらされ、入社後まもなく自律神経をやられた。社内のスポーツ同好会に入り、会社になじもうと彼なりに必死に努力したものの、うつ状態が続き、悩んだ挙句辞めることにしたという。
「俺はつくづくだめな人間だ」
暗い表情でうつむく友人に、私は言った。
「ばか、悪いのはお前じゃなくて、会社だ。というより社会の仕組みが問題なんだ。お前は社会の犠牲者なんだよ」
すると友人はひょいと顔をあげて、まじまじと私の顔を見た。そして「お前はいいなあ、そんなふうに考えられるなんて」と羨ましそうにつぶやいた。
そのとき、「あれ、こいつと俺とは基本的な発想がまったく違うようだ」と気づかされた。ばりばりの左翼だった若いころ、私は「個人の不幸は社会のせい。みんな社会が悪いのさ」と思っていた。社会を変えればすべてが解決すると。
ケン・ウィルバーは、「何故に人間には自由がないか」という問いに対して、客観的理由と主観的理由の二つの答え方があるという。
「客観的理由はルソーからはじまりマルクスに至って今日ではいわゆる『リベラル』な政治思想や人間中心的な心理学、哲学となっている。この考え方によると、人間はもともと自由で善良で愛にみちているが社会や政治という客体世界のなかで不平等や抑圧や悪意を身につけるとする。(略)つまり、自由がないのは外部世界の客観的状勢のなせるわざである、と。(略)
ここから、外部世界を変えて不自由の原因を取り除けば人間は自由になるとする考えが生まれる。(略)政治体制や経済機構を変えて搾取をなくし、万人が自然の恵みにあずかれるよう努力がなされる。これは、マルキストから社会主義者、リベラル、アメリカの民主党につらなる思想である」。
コミュニストからアメリカ民主党までふくむ「左派」は、ざっくりと、個人が不幸なのは社会のせいだと考える人たちなのである。私もその一人で、高校時代、水俣病の悲惨を知って衝撃を受け、弱者をここまで追い詰める世の中は許せないと、激しい義憤にかられたのが転換点だった。
「何故に人間には自由がないか」に対するもう一つの答えは、「ホッブスやバーク、フロイトや民族学者、政治上の保守主義者」たちが支持する主観的な理由だという。それは―
「人間が自由をもたないのは客体的社会構造に原因があるよりは人間の本性に由来するとする。(略)悪しき人間の本性が不自由の源であり、残忍さや悪や不平等も人間から生じるとする」。真の自分が統制できないところに問題があるというのである。
「事態を少しでも改善するためには統制のうえに統制を重ね、法律と合理性と規則で内面の殺人鬼を制止していく必要があるとされる」。「不平等や社会の不正義は避け得ない」のだから、「(エドモンド・バークは)社会機構を変えるための革命は無意味であり、革命があっても人間の本性が変わらない限り社会は良くならないとする。むしろ社会組織がゆれ動けば狂気や無政府状態のなかで人間の状況は悪化すると考えられる。したがって社会機構がある程度公正なものならばむしろ手を加えないほうがよいとする保守主義となる」。(以上引用はケン・ウィルバー『エデンから』)
こうして、政治的な右と左は、人間の苦しみの根本原因を内に求めるか外に求めるかという点で大きく分かれるという。左派は、主要な原因を客観的な社会制度に、保守派は、その人自身に置きがちである。左派は、「あなたが貧しいのは社会に抑圧されているからだ」と考え、右派は、「あなたが貧しいのは怠け者だからだ」と言う傾向があるというわけだ。それぞれが、それだけで十全でないことは明らかだと私が気づくのには、かなりの時間が必要だった。
タイで仏教と出会う
私は映像通信社に就職し、三十代の十年間、東南アジアに特派員として駐在し、うち七年間をタイで過ごした。学生時代からデモや集会、署名、選挙に明け暮れ、政治活動に没頭してきた私だったが、すでに既存の社会主義には幻滅し、思想的な軸を喪失して揺れ動いていた。外国暮らしで環境が激変したことも手伝い、ある意味、人生の混迷期にあった。
そんなとき知り合ったのが、タイで仏門に入った日本人青年、坂本秀幸君だった。社会的な関心が高く、タイの農村開発をめざすNGOで活動していたが、やればやるほど疲弊する状況に追い込まれていた。失意にあった彼は、仏僧の姿を見るうち、「心の開発」が必要と思い立ち得度したという。
タイの首都バンコクから遠く離れた田舎に彼の寺を訪ねると、そこは静かな森の中で、僧たちはそれぞれ小さな僧房に寝泊まりしていた。
「葬儀や村の儀式に招かれる以外は、僧房の外に出るのは朝の托鉢くらい。毎日が瞑想三昧で、実に楽しいよ」と彼は言う。オレンジ色の袈裟を身につけ、頭髪と眉を剃った彼の顔が晴々していて、羨ましく思ったことを覚えている。人生に悩み、社会に適応することに疲れた坂本君は、ここ草深いタイの寺に心安らかに生きる自分の居場所を見つけたようだった。
タイの仏僧の日常をテレビなどで紹介する場合につく「厳しい戒律が云々」との決まり文句に反して、彼は毎日が「楽しい」と言う。それがとても印象的だった。ちなみに彼、坂本君はいまやテラワーダ瞑想の指導者として知られるプラユキ・ナラテボー師である。プラとは僧という意味で、ユキは本名の秀幸からとったもの。毎年日本に帰ってきて瞑想会や講演、リトリート指導を精力的に行っている。
仏僧になったばかりの坂本君が発した「楽しい」の一言は、抹香くさい、堅苦しくて陰気な仏教のイメージを一新するものだった。仏典をみると、仏教の中核には、「楽しく生きよう」というメッセージがある。
お釈迦さま本人も楽しく生きていたようだ。
「怨みをいだいている人々のあいだにあって、怨むこと無く、われらは大いに楽しく生きよう」
「悩める人々のあいだにあって、悩み無く、大いに楽しく生きよう」
「貪っている人々のあいだにあって、患い無く、大いに楽しく生きよう」(『ダンマパダ』15章「楽しみ」)
「われらは、何物をももっていないが、さあ、大いに楽しく生きて行こう」(『サンユッタニカーヤ』)
この場合の「幸せ」、「楽しみ」というのは、寒い夜、おでんで熱燗をキューッと・・みたいな、いわゆる「快」の楽しみとは違うようだ。
仏典に「やすらぎにまさる楽しみは存在しない」とあるように、「やすらぎ」を意味すると思われる。この「やすらぎ」は、サンスクリットの “santi “(サンティ)で平和と言う意味にもなることばだ。心が安らかで穏やかになった状態なのだろう。修行すれば、少なくとも自分個人にとっては、安らいだ、気持ちの良い心境を得られるらしい。坂本君のおかげで、タイの仏教に、日本の仏教にはない魅力を感じた。私も瞑想三昧の暮しを体験したい。しかし、仕事があり家族もいる身、得度するわけにはいかなかった。
チベット仏教で知った「覚る」可能性
九二年、私は東京本社から、テレビ番組向けに、インドの亡命チベット人コミュニティを取材するよう指示を受けた。
チベットでは五九年、中国共産党の統治への抵抗運動が起き、これを軍が弾圧して多くの犠牲者が出た。現ダライ・ラマ法王(十四世)はチベットを脱出してインドに亡命、彼に続いて多くのチベット人がインドに逃れた。私はインド各地に住み着いたチベット人のコミュニティとそこに息づくチベット仏教を二週間にわたって取材することになったのである。
取材当時も峻険な山岳地帯を徒歩で越えてインドに亡命してくるチベット人は絶えず、インド北部ダラムサラの「チベット亡命政府」にはダライラマ法王に謁見しようと長い列ができていた。法王が一人ひとりに言葉をかけて苦労をねぎらうと、亡命者たちはありがたさに感極まって涙にくれるのだった。法王を単独インタビューする機会にも恵まれ、チベット仏教の世界を垣間見ることになった。
タイと違ってチベット仏教では、今生で覚りに至ることが可能だとされる。私の取材中の通訳兼ガイドをつとめてくれたチベット青年に「実際にブッダのように覚った人はいるのか?」と尋ねると、「たくさんいるよ」と言って、何人もの仏僧の名を挙げるのだった。また、インド山中の寒村に数万人の少数民族を集めて行われた「カーラチャクラ灌頂」の儀式を三日にわたって取材したが、そこで法王は何度も世界平和を語り広島の原爆投下にも触れた。個人の心の安らぎだけを目指すのではなく、世界を慈悲心で平和にしたいという法王の考え方に強く共感した。それは、私がもともと持っていた、民衆のために世の中を変えたいという心情にもひびくものだったからである。よし、チベット仏教を修行してみようと思い立った。
およそ半月にわたる取材を終えてタイに戻り、自宅のドアを開けた私の顔を見て妻は「あ、行っちゃってる」と思ったそうだ。面相が変わるほど、私はチベット仏教に〝かぶれた〟らしい。さっそくチベット瞑想の本を入手し、我流の瞑想修行を始めた。チベット仏教の瞑想は、曼荼羅を使ったりマントラを唱えたりとその種類や技法が非常に多様で奥深いのだが、私は簡単なイメージ瞑想から始めた。たとえば自分に害をなす人、憎らしい人などを思い浮かべ、彼らが前世で自分の親兄弟だったことをイメージする。あるいは目の前に若い女性が死んでいて、その肉体がどんどん腐敗し骨だけになっていく過程をリアルに想像していく、などである。イメージ瞑想によって慈悲や無常を身につけることをめざすのだという。瞑想しているとたしかに現世の価値観とは異なる世界を感じ、清々しい気持ちにはなることができた。
毎日、一人で瞑想を続けていたが、指導者もない状態ではすぐに限界がくる。マントラを覚えることは難しく、多数の菩薩に関する細々とした知識も要求され、行き詰まりを感じて来た。そんなとき、私の友人で定年後に世界中を旅して回っている人がバンコクに私を訪ねて来た。私が瞑想修行がうまくいかないとこぼすと、彼女はこう言った。
「あのね、簡単に覚れる方法があるらしいわよ。トランスパーソナルっていうんだって」
これが岡野先生との出会いにつながるのだから、ご縁とは不思議である。
(つづく)
創刊第二〇〇号記念寄稿集「サングラハと私の学び」
サングラハ教育・心理研究所会報『サングラハ』は、今回で創刊第二〇〇号を迎えました。一九九二年二月の第一号から三十余年、ご愛読いただいた読者の皆様のお陰であり、長年の御協力に感謝申し上げます。
これを記念し、研究所に御縁の深い方々、会員の皆様から「サングラハと私の学び」をテーマに、御寄稿をいただきました。心より御礼申し上げます。
今後とも、当研究所の活動へのご協力のほど、よろしくお願いいたします。
編集担当
(以下、本誌並びにこちらにて全文掲載)

ヒューマン・ギルド・ニュースレターより
昨年十二月二十日、アドラー心理学の研修団体「ヒューマン・ギルド」は当研究所を支援するための共催ZOOM企画を行い、多額の支援金を寄付してくださいました。これに関連して、研究所主幹代理の高世仁がヒューマン・ギルドの会報に二回寄稿しました。許可を得て転載します。
【ヒューマン・ギルド・ニュースレター2月号】
サングラハ応援プロジェクトへの感謝と新たなご案内
高世 仁
このたび、ヒューマン・ギルドはサングラハ教育・心理研究所と共催ZOOM企画を実施し、当研究所に多額のご寄付を贈ってくださいました。岩井先生はじめ、ヒューマン・ギルドのみなさんの温情あふれるご支援に心より感謝申し上げます。
サングラハ教育・心理研究所は、「どうしたら、人間すべてが、自分自身とも他者とも自然とも調和した、『仲よく楽しく生きて楽に死ぬ』ことができるような生き方に到達できるか、徹底的な探究を試み」、「そのことによって、人類の全体的変容―サヴァイバルになにほどか貢献すること」を理念として、岡野守也主幹が1992年に創設しました。そのために私どもは、霊性と理性の統合、自己実現から自己超越へという意味での〈意識の変容〉の理論と方法そしてその実践を探求してきました。
ところが一昨年、岡野主幹が難病のため闘病生活に入り、当研究所は運営上もまた財務上も厳しい状況を迎えています。今回の共催企画の実施とご寄付は私どもにとって大きな励ましとなり、今後の活動継続に希望を与えるものでした。
岡野守也主幹は往年、アドラー心理学を日本に導入すべく岩井先生とともに尽力したと聞いています。いわば長年の同志といってもよい関係にあります。また岡野主幹は一貫してアドラー心理学を人間成長に寄与するものと位置づけ、2004年、『アドラー心理学への招待』(アレックス・L・チュウ著)を翻訳して刊行(金子書房)、2010年には『仏教とアドラー心理学』(佼成出版社)を上梓しています。人間の精神的成長と社会への貢献を謳うヒューマン・ギルドと当研究所は設立理念に共有するものがあると認識しています。
「まさかの友こそ真の友」と言いますが、このたび当研究所の厳しい状況に手を差しのべてくださったヒューマン・ギルドのみなさんに私どもは恩義を感じております。そこで、感謝の気持ちを込めて、また今後の〝友情〟の深まりを祈念し、ふたたび共催ZOOM企画を実施し、そこで当研究所主幹代理をつとめる私、高世仁(たかせ・ひとし)が講演させていただきます。
私はジャーナリストとして、一昨年秋にウクライナを取材しました。「平和」ではなく「勝利」を求めるウクライナの人々に接し、「もし、ここが日本なら自分は戦うのか」と自問せざるを得ませんでした。日本は自国が侵略されても抵抗する人は13%と世界最低。「愛国心」に強い忌避感を持つこの日本的「平和主義」とはいったい何か。ウクライナ戦争は、私たちの心のありようを鋭く問いかけてきます。私は多くの人に考えてもらおうと昨年末『ウクライナはなぜ戦うのか~ジャーナリストが戦場で見た市民と愛国』(旬報社)を出版しました。
講演のタイトルを「ウクライナ戦争が問う日本の〝こころ〟―アドラー心理学の『共同体感覚』とサングラハの『コスモロジーの創造』に関連して」とし、みなさんに問題提起したいと思います。みなさんとお会いするのを楽しみにしています。
(注)この二回目の共催企画に寄せられた支援金もご寄付いただきました。
【ヒューマン・ギルド・ニュースレター3月号】
著者による本の紹介:『ウクライナはなぜ戦いつづけるのか~ジャーナリストが戦場で見た市民と愛国』(旬報社)
高世 仁
私は二三年秋にウクライナを取材し、前線での兵士の戦いぶりや銃後の市民の抵抗の実態に触れ、大きな衝撃を受けました。それはロシアの侵略に向き合う彼らの価値観が、日本に住む私たちのそれとは全く異なることに気づかされたからです。
ウクライナの人々は、政府の汚職体質や大統領の無策を大っぴらに批判し、「政府も大統領もあてにしない」と公言して自発的にロシア軍と戦っていました。あるコメディアンは「戦争に疲れた市民に笑いを提供することが私の戦いです」と語っていましたが、一人ひとりが自分の専門や能力をいかして抵抗を続けています。
政府のケアが届かない兵士や市民を多くのNGOが支援し、戦時下にもかかわらず、世界の報道の自由度ランキングでは年々順位を上げ、日本を抜き去りました。市民社会がしっかりと根付いたうえで、同じ国民としての同胞意識が根強い抵抗を支えていました。
ひるがえって、日本に住む私たちはどうでしょうか。自国が侵略されたとき「戦う」と答えたのは13%で世界77カ国中最低、「戦わない」が49%で世界最高、さらに「わからない」が4割近くでこれも世界最高。これは、平和に対する何らかの〝信念〟からではなく、「国のことなどどうでもいい」、「大事なのは自分(だけ)」という人生観がベースになっているからではないでしょうか。
私たちの平和に関する意識は、実はエゴイズムにもとづく、とても薄っぺらいものなのではないか。私はウクライナを旅する間、「もしここが日本なら、自分はどうするだろうか」と自問せざるを得ませんでした。
私は一九五三年生まれで、戦後民主主義教育を受けてきた世代に属します。高校に入るまで学校で日の丸を見たことがなく、「君が代」も大相撲の千秋楽で聞くだけでした。「愛国心」は持ってはいけないものと思い、「国のため」とは、国家権力が個人を抑圧するスローガンだと信じてきました。
そうした感覚が、かつての軍国主義の否定として意味のあったものであることは理解しています。しかし、一方で同じ国民としての同胞意識を置き忘れてきたのではないでしょうか。
私たちは必ず特定のアイデンティティのもとで生きています。たとえば私なら、二人の娘の父、国分寺市の市民でありジャーナリスト、そしてサングラハの主幹代理であり…と続きます。
現在の人類の発展段階においては、ある国の国民であるというアイデンティティは、善し悪しは別にして、きわめて重要な意味を持っています。
日本に住む私たちは、「同胞」の運命を共有し、この国を良くしようと真剣に思っているでしょうか。私はそんな問題意識をもって『ウクライナはなぜ戦い続けるのか~ジャーナリストが戦場で見た市民と愛国』(旬報社)を昨年末、上梓しました。
アイデンティティにおける運命共同体としての意識は、アドラー心理学でいう「共同体感覚」からはどのように評価されるのかなど、ヒューマン・ギルドのみなさんとも語り合ってみたいテーマです。
編集後記
今回、創刊第200号を迎え、30年余の歴史を振り返る意味での、通常とは異なる記念寄稿集としています。療養中の岡野主幹からは、研究所の歴史の節目として、自らの思想的な歩みを振り返るメッセージを受け、掲載しております。出生、信仰、そして思想及び時代状況と、天命によって担われた「重荷」の背景を、会員として再確認させていただきました。私たちも能う限り受け継いでいきたいと思います。高世主幹代理による、ご自身がサングラハに関わるまでの思想的変遷を記された連載がスタートしました。今回、第一線のジャーナリストとしての活動の傍ら敢行された瞑想修行について、とても興味深い内容となっています。会員やご縁ある皆様から、創刊第200号記念として、「サングラハと私の学び」と題したご寄稿をいただきました。それぞれの方のサングラハをめぐる出会いや学び、そして現在が垣間見えてきます。お寄せいただいた方々には、まことにありがとうございました。また、協賛いただいているヒューマン・ギルド社のニュースレターから、高世主幹代理による記事を転載しています。同社の多大なご支援・ご協力に感謝申し上げます。(編集担当)
会報誌「サングラハ」ご講読のご案内
会報誌「サングラハ」は、購読料5,000円で年6回隔月発行・お届けしています。
お問合せ・お申込みは、個別の号のお取り寄せのご相談などは、こちらの専用フォームをご利用ください。